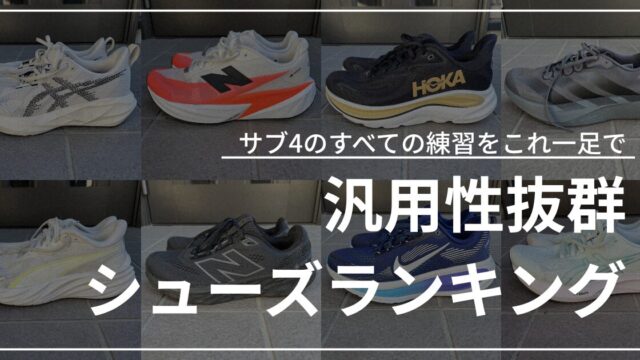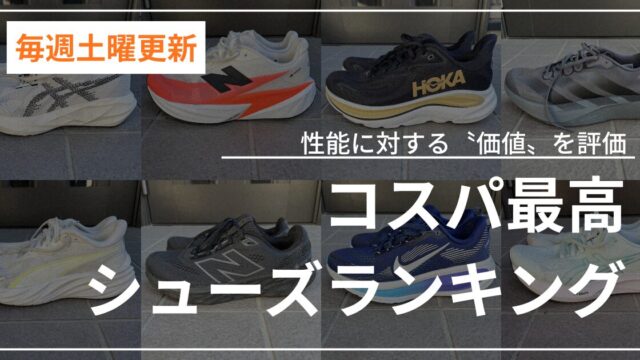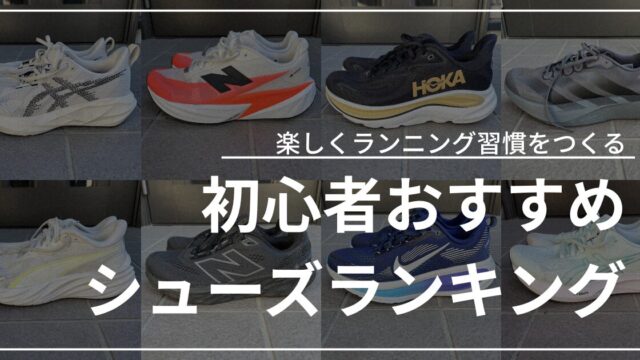仕事に家事にと忙しい日々の中で、ついついスマホにかじりついてしまいがち。
と悩んでいませんか。
自覚症状がなくても、気がつけば寝る直前までSNSやニュースを追い、多くの方が貴重な時間と集中力を“スマホ漬け”で消耗しています。
そこで注目されているのがデジタルデトックスです。デジタルデトックスとは、『スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器から意図的に離れることで心身をリセットすること』です。
そしてランニングはこのデジタルデトックスに最適な方法の一つと言えます。
走りながらスマホは触れないので、デジタルデトックスできるのは当然ですが、それ以上にランニングはデジタルデトックスの効果を飛躍的に増加させることができます。
この記事ではデジタルデトックスが必要な理由、そしてランニングがなぜデジタルデトックスに最適なのか、詳しく解説します。
ランニングを通じて、現代人の悩みの一つを解消していきましょう!
執筆者紹介
- 40代会社員ランナー(5人家族)
- ラン歴3年目
- 月間走行距離300km前後
- フルマラソン自己ベスト
4時間29分6秒
(第2回ひたちシーサイドマラソン)
〝楽に楽しくランニング〟をテーマに初心者ランナーに近い目線で発信します。
コメントもお気軽にお願いします。
更新の励みになります!
スマホ依存が奪う「時間」と「集中力」

気がつけば寝る直前までSNSやニュースを追い、貴重な時間と集中力を“スマホ漬け”で消耗していませんか?
現代人の多くは同じ悩みを抱えており、その背景にはスマホ依存による時間喪失と脳の疲労があります。
ここではスマホ依存の実態や脳への影響、そしてデジタルデトックスが注目される社会的背景について解説します。
スクリーンタイムの実態:総務省・民間調査の最新数字
総務省や民間の調査によれば、スマホやPCに費やす時間は年々増加しています。例えば、日本の総務省の調査では、スマホなどモバイル機器による1日のインターネット利用時間は平日平均約113分、休日は約139分にも及んでおり、年々増える傾向にあります(参考:スマートフォン利用時間の増減の要因)。
一方、世界的に見ると16~64歳のインターネットユーザーは1日平均6時間40分もスクリーンに向き合っているとの報告もあり、この数字は人生の17年間に相当するとされています。
17年もスマホを含むデジタルデバイスの画面をのぞき込んでいると思うとちょっと考えさせられますね・・・。
時間とパフォーマンスを蝕む「脳過労」のメカニズム
常時スマホをチェックする習慣は、脳に慢性的な負荷をかけています。その結果起こるのが「脳過労」と呼ばれる状態です。
脳過労とは脳の使いすぎで機能が低下した状態で、スマホ画面から大量の情報を高速処理し続けることで脳に疲労が蓄積します(参考:脳科学者に聞いた、スマホとのベストディスタンス。脳過労の症状と対策とは?)。
特に意思決定や集中力をつかさどる前頭前野が疲弊し、記憶力の低下やイライラしやすくなる等の症状が現れます。実際、スマホ過剰利用による脳過労では
- 1時間前に聞いたことを思い出せない
- 些細なことで怒りが抑えられない
- 判断力が鈍る
などの弊害が報告されています。慢性的な脳疲労は仕事のパフォーマンス低下にも直結し、集中力や意欲を奪ってしまうのです。
デジタルデトックスが注目される3つの社会的背景
こうしたスマホ依存の弊害を受け、近年「デジタルデトックス」が社会的に注目されるようになりました。その背景には大きく3つの要因があります。
- SNS疲れとスマホ依存の顕在化:便利な反面、SNSを長時間眺めることによるストレスや、「常に通知に追われる生活」への疲弊感が広がりました。スマホ依存やSNS依存が新たな社会問題として浮上し、精神衛生への悪影響が無視できなくなっています(参考:デジタルデトックスとは? 企業が”通知を減らす”時代の新たなマーケティング戦略)。
- コロナ禍でのオンライン化促進:在宅勤務や巣ごもり生活が増えたことで、以前にも増して一日中デジタル機器に触れる時間が増加しました。Zoom会議やチャット対応などでオンオフの境目が曖昧になり、心身の疲れを感じる人が増えています。この結果、「意識的にオフラインになる時間」を求める動きが強まりました。
- ウェルビーイング志向の高まり:働き方改革やメンタルヘルス重視の流れの中で、テクノロジーとの健全な付き合い方を模索する人や企業が増えています。大手企業が通知を削減する試みを始めたり、デジタルウェルビーイング(デジタルとの向き合い方の健康)という概念が普及したりしつつあります。こうした中、デジタルデトックスは自己管理やストレス対策の一環として受け入れられてきたのです。
デジタルデトックスとは?

現代のスマホ社会において、「デジタルデトックス」という言葉を耳にする機会が増えました。このデジタルデトックスとは一体何なのでしょうか?
ここではその定義や歴史から、必要性、効果、さらには批判的な視点まで、デジタルデトックスの全体像を押さえておきましょう。スマホ漬けの日常から抜け出すヒントが見えてくるはずです。
定義と歴史:現代人の日常的なセルフケア
デジタルデトックスとは、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器から意図的に離れることで心身をリセットすることを指します(参考:【デジタルデトックス】 ~1分で分かるキーワード #263)。簡単に言えば「デジタルを断つこと」であり、その期間中はSNSやゲームなど一切のデジタル操作を控えます。
元々2010年代半ば頃から欧米で注目され始め、日本でも2016年には「日本デジタルデトックス協会」が設立されるなど、概念が広まりました。Wikipediaでも「現代ではデジタル機器やインターネットに費やす時間が増えたため、こういったデトックスが人気になっている」と解説されており、スマホ時代の新しい休養法として定着しつつあります。
歴史的に見ると、当初は休暇や週末を利用してキャンプなどで完全オフラインになる取り組みが話題になりました。その後、ビジネスパーソンにも広がり、昨今では日常生活の中で数時間だけデバイス断ちをするミニデトックスも推奨されています。
2019年頃にはOxford辞典が「digital detox」を収録するなど一般用語化し、2020年代には自治体や企業がデジタルデトックスのイベントを開催するケースも見られます。つまりデジタルデトックスは、一過性のブームから日常的なセルフケア手段へと進化してきました。
必要性:スマホ依存がもたらす身体・メンタル・人間関係への影響
デジタルデトックスの必要性を理解するには、スマホ依存が及ぼす体と心、人間関係への悪影響を知ることが重要です。
スマホに没頭する生活が続くと、様々な不調がじわじわと蓄積していきます。その代表的な例を挙げてみましょう。
結構当てはまってドキッとする人も多いと思います。私も大体当てはまったので、気を付けていきます。
脳疲労/集中力低下
長時間のスマホ閲覧は脳を酷使し、脳疲労(デジタル疲れ)を招きます。前述の脳過労状態になれば集中力が続かず、仕事でもミスが増えることにもつながります。
「常に情報を追い続けなければ」という強迫観念が生まれ、マルチタスク状態で脳が休まらないのです。その結果、注意力散漫になり生産性も低下してしまいます。
実際にスマホ依存の成人では、脳の灰白質(かいはくしつ)が萎縮し意思決定能力に影響を及ぼすという研究も報告されています。このようにスマホの使いすぎは脳の構造と機能にまで負荷をかけ、休息なしではパフォーマンスが落ちる一方です。
「常に情報を射続けなければ」という強迫観念は心当たりあります。つい空いた時間はYoutubeで何かインプットしないと時間がもったいないという気持ちになってしまいます。
睡眠の質低下とブルーライト
寝る前のスマホ習慣は睡眠の大敵です。スマホやPCの画面が発するブルーライトは脳内で睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、体内時計を狂わせます。
夜にスマホを見続けると脳が昼間だと錯覚し、なかなか寝付けなかったり眠りが浅くなったりします。その結果、慢性的な睡眠不足や不眠症状に悩まされ、日中の集中力低下や気分の落ち込みにつながります。
また就寝直前までSNSをチェックする行為は脳を興奮状態にしてしまい、リラックスして眠りに入る妨げになります。質の良い睡眠を確保するためにも、就寝前のデジタルデトックスは必要不可欠なのです。
つい寝る前に見ちゃいます。SNSは何時までと決めないとダメですね。
肩こり・眼精疲労・姿勢崩れ
小さなスマホ画面を長時間見つめることは、身体にも負担をかけます。代表的なのが目の疲れ(眼精疲労)と肩こり、そして首や背中の姿勢悪化です。下向きでスマホを操作する姿勢が癖になると首のカーブが失われ、「ストレートネック(スマホ首)」状態になりやすくなります。
この姿勢では頭の重みが首・肩に何倍もの負荷をかけ、筋肉の緊張から頭痛や首・肩の痛みを誘発します(参考:スマホっくびって何?)。
私も整形外科でストレートネックと言われてしまいました。PC作業のやり過ぎで首から左腕にかけてしびれもあり、ここ2か月くらい悩まされてます。
また画面凝視による瞬き減少で目が乾燥し、ドライアイや視力低下のリスクも高まります。
さらに長時間同一姿勢でいると血流が悪化し、慢性的なコリや疲労感に繋がります。デジタルデトックスによってこれら身体への負荷を軽減し、本来の正しい姿勢と身体の軽さを取り戻すことが期待できます。
加えて、スマホ依存は人間関係にも影響します。食事中や会話中についスマホをいじってしまう「ながらスマホ」は、目の前の相手をないがしろにする行為です。ある研究では、配偶者との対話中にスマホに熱中すると夫婦の満足度が低下することが示されています。実際に「スマホに気を取られてパートナーを疎かにした」人は、関係満足度が下がり鬱傾向や人生への不満が高まるとの報告もあります。
デジタル過多な生活は人との絆を希薄化させ、心の健康にも影を落とすことになります。
効果とメリット:リラックス・創造性・家族時間の回復
デジタルデトックスを実践すると、心身に様々なポジティブな変化が現れます。その大きなメリットの一つがストレスの軽減とリラックス効果です。
デバイスから離れることで情報過多の状態から解放され、脳に休息の隙間(余白)が生まれるため、緊張がほぐれます。実際にデジタルデトックス後には集中力が高まりストレスが減ったという声が多く、心拍や血圧が安定するといったリラックス反応も報告されています。
さらに、創造性(クリエイティビティ)の向上も見逃せません。常時スマホ通知に追われる日常では、発想する余裕がありませんが、オフラインの時間は頭の中を整理したり新しいアイデアが浮かんだりする貴重な時間です。ある調査では、デジタルデトックスを行った後に生産性や創造性が向上し、家族とのコミュニケーションも改善したとの結果が示されています(参考:Studies on digital diet and digital detox: A meta-analysis)。情報の洪水から距離を置くことで、自分自身と向き合い創造的な思考が活発になるのです。
加えて、家族や友人との時間を取り戻せるのも大きなメリットです。スマホを見ない時間を意識的に作ることで、これまで画面に費やしていた時間をリアルな交流に充てることができます。その結果、人との繋がりからくる安心感や幸福感が高まります。
デジタルデトックスは、忙しい現代人に心のゆとりと人間らしいふれあいを取り戻してくれるのです。
デメリット・批判的視点:リバウンドや「完全遮断」の現実性
一方で、デジタルデトックスには批判的な視点やデメリットも存在します。まず指摘されるのが、効果の一時性(リバウンドの可能性)です。
短期間スマホ断ちをしても、その後元の生活に戻れば結局依存状態も元通りになりがちです。たとえば週末だけオフラインにしても、月曜からはまた長時間スマホ漬け…では根本的な解決にならないという指摘があります。
また現代社会では、仕事や連絡にスマホやPCは欠かせず「完全に遮断するのは非現実的」との批判もあります。SNSには人脈維持などの利点もあり、一概にゼロにすべきでないとの意見も専門家から出ています。
さらに、デジタルデトックスをストイックにやりすぎるとかえってストレスになる場合もあります。仕事上どうしてもデバイスが必要な人にとって、無理な断ちは現実的でなくフラストレーションがたまるだけかもしれません。
完全に断つというより、大事なのは適切な距離感ですね。しっかり管理して利用することが大切だと感じます。後述するデジタルミニマリズムという考え方でデジタルデトックスの効果を最大化できます。
ランニングが“動くデジタルデトックス”になる理由

デジタルデトックスの方法はいろいろありますが、その中でもランニングはスマホ漬けから解放される手段としてとても有効です。
実はランニングは「動的なデジタルデトックス」と呼べるほど、スマホ依存を断ち切り心身をリセットする効果があります。
ここではランニングが持つデジタルデトックス的メリットを、科学的な視点から紐解いてみます。
有酸素運動による脳機能リセット(海馬体積+α波)
ランニングのような有酸素運動は、脳をリフレッシュさせる強力な手段です。まず注目すべきは脳の記憶中枢である海馬への効果。有酸素運動を継続すると海馬の体積が増大することが研究で分かっており、あるメタ分析では海馬体積が最大3.2%増加したとの報告もあります(参考:脳とこころを動かす「運動」の力――認知機能からメンタルヘルスまで)。海馬が大きくなることは記憶力や学習能力の向上に繋がり、脳の若返り効果すら期待できます。
さらに、有酸素運動時には脳内でα波が増加します。α波はリラックスしつつ集中している時に出る脳波で、ストレス軽減や創造性向上に寄与します。実験でも、運動習慣のない成人が30分間エアロバイクを漕いだところ、運動中~運動後にα波が13.5%増加し、幸福ホルモンであるβエンドルフィンは75%も増えたとされています(参考:若返りをもたらす「ランナーズ・ハイ」)。
つまりランニングは脳に適度な刺激と快感を与え、精神を安定化させるのです。
走り終えた後に爽快感や前向きな気持ちになるのは、科学的にも裏付けられているんですね!
このように、ランニングによる有酸素運動は脳のデトックス(老廃物除去)と再活性化を促し、スマホで疲れた脳をリセットしてくれます。
スマホを触れない物理的隔離効果
ランニング中は物理的にもスマホから隔離されます。走っている最中にスマホの画面をスクロールするのは難しく、必然的に「ながらスマホ」から解放されます。
ポケットにスマホを入れていても、走行中は通知を確認する余裕がないため、結果的にスマホ断ちの時間を強制的に作り出せるのです。
実際走っている間はスマホの画面を見ることがないので貴重なデジタルデトックスの時間だと体感しています。外の景色、空気を感じながら走ると心も開放的になりスッキリとしてきます。
ランニング中はオーディブルで聞く読書をしていることが多いですが、あえてオーディブルを聞かずに走るとリフレッシュ効果も高いです。目的に応じてランニング方法も使い分けるといいですね!
ランニングは「手と目」をスマホから遠ざける物理的な拘束になります。特に屋外で走る場合、景色や足元に注意を払うため、自然とスマホの存在を忘れられます。これによりスマホへの強い欲求を断つ練習にもなります。
ランニング習慣でデジタルデトックスの効果を体感し、私生活に取り入れる練習にしていきましょう!
朝ランが体内時計を整え夜間のスクリーン欲求を抑える
特に朝のランニングには、夜のスマホ欲求を和らげる効果があります。朝起きて日光を浴びながら走ることで、乱れた体内時計をリセットできるからです。
人間の体内時計は朝の光刺激でスイッチが入り、約15~16時間後に眠気を誘うメラトニンが出るリズムになっています。
加えて起床直後に運動することで、体も頭も一日をスタートさせるスイッチが入り、体内時計がリセットされます。
朝日を浴びてのランニングは、夜ぐっすり眠るための一石二鳥の習慣といえます。
夜寝る前はどうしても少しスマホを触ってしまいますが、少なくとも触る時間は短くできています。
体内時計のせいで9時には眠くなるというのもありますし、「せっかく体内時計をリセットしたんだから、最高の睡眠のためにもスマホを触る時間を減らそう」という意識が働くというのも大きいです。
実際朝ランの習慣を取り入れたことで、夜の寝つきはよくなっていますし、スマホを触る時間も短くなりました。
朝ランが定着すれば、夜間のスクリーンタイムを減らし睡眠の質を高める好循環が生まれます!
走行中の“没入”がマインドフルネスを生む
ランニングは単なる運動に留まらず、マインドフルネス(今この瞬間への集中)の実践にもなります。
一定のリズムで走り続けていると、次第に呼吸や足音、自分の鼓動だけに意識が向かい、雑念が消えていく瞬間を経験したことはありませんか?これこそが没入の境地であり、瞑想と同様に心を整える効果があります。
専門家の中には「走っているときこそ、マインドフルネスへの最大の近道」だと指摘する人もいます。一歩一歩に意識を集中させ、今この瞬間の感覚に没頭することは、狩猟本能に根ざした人間本来のゾーン(集中状態)に近く、脳のパフォーマンスを最大限に引き出す精神状態だというのです(参考:【ランニングは最高のアンチエイジング 22】ランニングはマインドフルネスを生む!)。
ランナーは知らず知らずのうちに、走ることで脳の疲労を減らし、集中力や幸福感を高めるマインドフルネス効果を得ています。
朝のランニング中に仕事の悩みを忘れて風や鳥の声に意識を向けることで、心がスーッと軽くなります。こうしたランニングの没頭感は、デジタルデトックスで得たい「今ここに集中する感覚」を自然に味わわせてくれます。
スマホ依存が招く7つの健康リスク

スマホに依存した生活を続けると、知らず知らずのうちに様々な健康リスクを招きます。
特に働き盛りの40代が注意すべき代表的なリスクを7つ挙げ、それぞれ簡潔に解説します。
デジタルデトックスへのモチベーションを高める意味でも、自分に当てはまる症状がないかチェックしてみましょう。
疲労蓄積と集中力ダウン
長時間のスマホ利用は心身の疲労を蓄積させ、慢性的な疲れやすさを生みます。特に脳は休む間もなく情報処理を強いられるため疲弊し、集中力の低下やミスの増加といった形で現れます。
勤務時間中についスマホをチェックする習慣がある人は、その都度注意力が寸断され仕事のパフォーマンスが落ちてしまいます。
夕方になるとどっと疲れる、休日もなんだか頭が重い…
という人は、スマホ脳疲労が原因かもしれません。蓄積した疲労は質の良い休息でリセットしない限り抜けにくく、慢性疲労症候群のような状態になるリスクもあります。
眼精疲労・頭痛・姿勢崩れ
前述の通り、スマホの見すぎは目・頭・首肩に大きな負担となります。画面を凝視し続けることで眼精疲労が起こり、ひどい時はピントが合いにくくなったり、緊張型頭痛を引き起こしたりします。
また首を前に突き出す姿勢(スマホ首)は肩こりや頭痛の原因となり、背中が丸まることで呼吸が浅くなってしまうこともあります。実際、スマホ等の長時間使用は肩首の筋肉を固め血行不良を招き、頭痛持ちになる人も増えています(参考:スマートフォンやパソコンと頭痛の関係)。
姿勢の崩れは見た目の印象だけでなく、将来的な脊椎への負担からヘルニアや神経痛などを誘発する恐れもあるため油断できません。
睡眠障害とホルモン分泌の乱れ
寝る直前までスマホをいじる習慣は、睡眠障害を招く典型的な原因です。ブルーライトによるメラトニン抑制で入眠が遅れるほか、夜中に通知音で目が覚めてしまうケースもあります。
慢性的に睡眠不足になると、自律神経やホルモン分泌のリズムが乱れます。例えば睡眠不足はストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を増やし、さらにそれが不眠を招くという悪循環に陥りがちです。
また、夜更かしすると朝に太陽光を浴びる時間が減り体内時計がずれてしまい、昼間にボーッとする・夜に目が冴えるといったリズム障害が起こります。
これらは放っておくと不眠症やうつ症状に発展する可能性もあるため、早めの対策が必要です。
肥満・運動不足
スマホに費やす時間が長い人ほど、身体活動量が減って肥満になりやすいことが研究で示唆されています。
極端な例では、1日5時間以上スマホを使う人はそうでない人に比べて肥満になるリスクが43%増加したとの報告もあります(参考:1日5時間以上のスマホ使用で肥満増加の可能性)。スマホに夢中になっている間は座りっぱなし・食べ過ぎになりやすく、甘い飲み物やスナックを摂取する頻度も増える傾向があるためです。
結果としてメタボリックシンドロームや糖尿病のリスクも高まります。
運動不足は筋力低下や代謝ダウンを招き、余計に太りやすい悪循環に。
特に中年世代では「仕事で疲れて運動する気力が出ず、ついスマホで休憩」が続くと、気づいたときにはお腹周りに脂肪が…という事態も十分あり得ます。
メンタル不調・うつ傾向
スマホ依存は心の健康にも影響します。常にSNSで他人の生活と比較したり、ネガティブニュースを浴び続けたりすると、不安感や自己肯定感の低下につながります。
研究でも、スクリーンタイムの長さとうつ症状の出現率には正の相関があることが示されています。特にSNSの過剰使用は自尊心を傷つけ、「自分だけが取り残されているのでは」という恐怖心を引き起こしやすくなります。
こうした精神的ストレスが積み重なると、やがて抑うつ状態に陥ったり、意欲の低下や怒りっぽさなどのメンタル不調として現れます。
スマホから一時距離を置くだけでも気分が軽くなる経験をした人は多いでしょう。心の健康維持のためにも、デジタルとの適度な距離感は必要なのです。
人間関係の希薄化
スマホに没頭する時間が増えるほど、リアルな対人関係はおろそかになりがちです。家族と同じ部屋にいても各自がスマホを見て会話がない、友人と会っていても通知が気になって上の空、といった状況に心当たりはないでしょうか。
こうした「ながらスマホ」は相手に「自分は大事にされていない」と感じさせ、人間関係の満足度を低下させます。
前述の研究の通り、配偶者をスマホで無視する行為(ファビング)は夫婦間の幸福度を下げ、ひいては自分自身の人生満足度も下げてしまいます。
人は本来、顔を合わせて言葉を交わす中で安心感や絆を深めるもの。スマホ中心の生活が続けば、孤独感や家族との断絶感が高まり、いざという時の支え合いも希薄になってしまいます。
事故・ヒヤリハットの増加
最後に、スマホ依存が招くリスクとして事故の危険があります。
歩きスマホや運転中のスマホ操作による事故ニュースは後を絶ちません。
実際、警察庁のデータではスマホ等を使用している場合、使用していない場合に比べて交通死亡事故率が約2倍になると報告されています(参考:歩きながら・運転しながらのスマートフォンは大変危険です!)。
歩行中でも視野が極端に狭まり、電柱や他の歩行者と衝突するトラブルが多発しています。東京消防庁のまとめによれば、歩きスマホで転倒して救急搬送された例も多数あり(参考:歩きスマホ等に係る事故に注意!)、最悪の場合命に関わる怪我を負うケースもあります。
スマホを安全に使うためにも、そもそも使わない時間を設けるデジタルデトックスは有効な自衛策となります。
今日からできる「ラン×デジタルデトックス」5ステップ

スマホ依存を断ち切り、ランニング習慣で心身をリフレッシュするために、誰でも今日から始められる5つのステップを紹介します。
忙しいビジネスパーソンでも実践可能な、小さな工夫と習慣づくりの方法です。一つひとつはシンプルですが、継続すれば確実に効果が現れます。デジタル漬けの毎日から抜け出すロードマップとして活用してください。
STEP1 使用状況を可視化する(スクリーンタイム計測)
まずは現状把握から始めましょう。スマホの使用状況を“見える化”することで、自分がどれほどスマホに時間を取られているかを自覚します。
具体的には、スマホの設定にある「スクリーンタイム」や「デジタルウェルビーイング」機能を使って、1日の利用時間やアプリごとの使用時間を大体でいいので把握しましょう。
どんなアプリで時間を使っているのか見えると「1日に何時間もSNSを見ていた…」など、数字で突き付けられると問題意識が高まります。
この可視化こそがデジタルデトックスの第一歩です。大体傾向が見えてきたら、よく使うアプリを見る頻度を落としていきましょう。「このアプリでスクリーンタイム長くなってるんだよな」という意識があるだけで利用時間を減らすことができます。
またダラダラ見てしまうのもスクリーンタイムが長くなってしまう理由の一つ。「15分だけ」と時間を決めてその時間に逆に集中して利用する。そして一度距離を置く。こういう使い方をすることで、時間も有効に使えますしスクリーンタイムも短くすることができます。
ちなみに私は一日平均のスクリーンタイムは約4時間・・・。半分はYoutubeで半分Xといった感じでした。Youtubeはほぼ聞き流しで画面は見ていないとはいえ、一日の1/6をスマホとともに過ごしていると思うとちょっと反省したいと思います。
STEP2 週2回・朝ラン30分をカレンダーに固定
次に、ランニング習慣をスケジュール化します。忙しい人ほど「時間があれば走る」ではなく、最初から予定表に入れてしまうのがコツです。
まずは週2回、朝に30分走ることを目標にしましょう。例えば毎週火曜と土曜の朝7時~7時30分はランニングタイム、とカレンダーに予定ブロックを固定します。
朝ランをおすすめするのは前述の通り、体内時計リセット効果が高く夜のスマホ欲求を抑えられるためです。
朝走ると決めてしまえば、前夜は自然と早寝しようという気持ちになり、夜更かしスマホを見る時間も減ります。
30分のランニングであればシャワー等含めても1時間弱。週2時間の自己投資で、心身の健康とデジタルデトックスが得られる計算です。
ペースはゆっくりジョギングでOK。重要なのは「決まった日に必ず走る」という習慣化です。会社の会議や商談と同じ扱いでスケジュールに入れてしまい、他の用事を入れないようにします。こうすることで三日坊主を防ぎ、ランニングが生活の一部となっていきます。
週2回が慣れてきたら週3回に増やしたり、距離を伸ばしたり、自分なりに調整してみましょう。
STEP3 スマホ封印テク:機内モード/自宅置き/緊急設定
ランニングを効果的なデジタルデトックス時間にするために、意図的にスマホを封印する工夫をしましょう。以下のテクニックを状況に応じて使ってみてください。
- 機内モードにする:走る前にスマホを機内モードに切り替えておけば、通知や着信が一切来なくなります。音楽を聞きたい場合も、事前にオフライン再生リストを用意すればOK。走っている最中に余計な通知に邪魔されずに済みます。
- スマホを家に置いていく:思い切ってノーフォンランに挑戦するのも手です。スマホを持たずに走ると最初は不安かもしれませんが、その分周囲の景色や自分の呼吸に集中できます。「走っている間は誰とも連絡が取れなくて当たり前」と割り切りましょう。短い時間なら緊急連絡が来る可能性も低いはずです。
- 緊急連絡用の設定:仕事柄どうしても「完全無視」はできないという場合は、スマホのおやすみモード/通知フィルターを活用しましょう。特定の緊急連絡先(家族や職場)からの電話だけ鳴る設定にし、それ以外はすべてミュートします。これなら本当に急を要する連絡だけ受け取れ、不要な通知はカットできます。
これらを駆使して、ランニング中は物理的・心理的にスマホとの距離を置くことがポイントです。スマホを完全に手放す時間を作ることができれば、その時間帯は完全にオフラインに没頭できるようになります。
STEP4 ラン後10分ストレッチで思考整理
ランニング直後は汗を流して終わり…ではなく、デジタルデトックス効果を高めるアフターケアを行いましょう。おすすめはストレッチ10分で思考整理です。
まず、ランニング後のストレッチを10分間行います。太ももやふくらはぎ、腰回りなどをゆっくり伸ばし、クールダウンしましょう。体のケアをすることで筋肉痛予防になるだけでなく、心拍が落ち着きリラックスモードに入れます。ストレッチ中もスマホは見ず、深呼吸しながら今日の走りを振り返ってみてください。
走っている最中は、「モヤモヤしていた案件の解決策が浮かんだ」「週末に家族と行きたい場所を思いついた」など、新たな気付きが出てくることが多いです。
そういった気づきを落ち着いて整理するのに最適な時間になります。
可能であれば紙のノートに書いてみることもおすすめです。デジタルではなくあえてアナログな紙とペンを使うのがミソです。ノートにはその日の気分や思いついたこと、仕事のアイデア、明日のToDoなど何でも書いて構いません。ランニング直後は脳が活性化しクリアな状態なので、頭の中を整理する絶好のタイミングです。スマホのメモアプリではなく紙に書くことで、余計な通知に邪魔されず思考を深掘りできます。
STEP5 休日は“アナログ体験”を家族と共有(ハイキング・料理)
平日のルーティンに加え、週末休日の過ごし方もデジタルデトックスを意識してみましょう。せっかくのオフに一日中スマホやテレビで過ごすのはもったいないですよね。おすすめは家族や友人と一緒にアナログな体験をすることです。
例えば、天気の良い休日には近郊へハイキングに出かけてみてはいかがでしょうか。自然豊かな場所を歩けばリフレッシュでき、もちろんスマホを見る暇もありません。山歩きや公園散策中は会話も弾み、家族との絆も深まります。都会でのランニングとは一味違う景色を楽しむことで、脳に新鮮な刺激を与えられるでしょう。
また、アウトドアでなくても料理やDIY、ボードゲームなど、手を動かすアナログな趣味を家族とやってみるのも良いですね。一緒に料理を作ればコミュニケーションが増え、美味しい食事で満足感も得られます。子どもと工作をしたり、あえて電源を切って読書会を開いたりするのも面白いでしょう。
ポイントは「スクリーンを介さない時間をみんなで楽しむ」ことです。最初はスマホが気になるかもしれませんが、没頭できる遊びや体験があれば自然と忘れられます。
月に一度は“デジタルオフデー”を作って、外出プランやイベントを企画してみるのも面白いと思います。そうしたアナログ体験の共有が、スマホ以上に豊かな充実感をもたらしてくれるはずです。
デジタルミニマリズムという選択肢

デジタルデトックスに取り組む中で、より長期的な視点としてデジタルミニマリズムという考え方にも触れておきます。
デジタルミニマリズムは日常的にデジタル機器の使用を最小限に抑える生活哲学で、デジタルデトックスと似ていますが少しアプローチが異なります。
ここでは両者の違いと補完関係、そしてミニマリズムを実践する具体的なコツを紹介します。
デジタルデトックスとの違いと補完関係
デジタルミニマリズムとは、スマホやPCとの付き合い方を見直し「自分にとって本当に必要なものだけ」を使うようにする生き方です。
しばしばデジタルデトックスと混同されますが、両者には明確な違いがあります。デジタルデトックスが1日や数日間の短期集中的なデバイス断ちで心身を休めることを目的とするのに対し、デジタルミニマリズムは日常生活において常に利用を取捨選択し、デジタルとの距離感を最適化する「長期的な習慣づけ」です。
デジタルデトックスは一時的にストレスをリセットする効果がありますが、元の生活に戻ればまたスマホ漬け……というリバウンドの課題がありました。
これに対しデジタルミニマリズムは、デトックスで気づいた「本当に必要なものと不要なもの」の仕分けを日々続けていく点に意義があります。例えば、デトックスでSNS断ちの爽快感を知った人が、その後もSNSの利用頻度を減らすなど生活習慣に組み込む形でデジタルミニマリストになるケースが多いです。
つまりデジタルデトックスとデジタルミニマリズムは、短期と長期の関係にあります。短期デトックスで得られた解放感や気づきを踏まえて、長期的にデジタル依存を防ぐのがミニマリズムの役割です。
どちらが欠けても片手落ちになりかねません。
まずデジタルデトックスでスマホ無しの爽快さを体験し、その後はミニマリズム的に必要最小限のデジタル利用を心がける……というように、両方をバランスよく取り入れるのがおすすめです(参考:デジタル・ミニマリズムとは?自分の時間を大切にする方法)。
ミニマム化チェックリスト(アプリ整理・通知断捨離)
それでは具体的にデジタルミニマリズムを実践するにはどうすれば良いでしょうか。まず手始めにできるのが、スマホ内の「デジタル断捨離」チェックリストに沿った整理です。以下の項目を一度試してみてください。
- 不要なアプリを削除:ホーム画面に並ぶ大量のアプリは、それだけで誘惑になります。最近使っていないゲームやSNSアプリ、重複する機能のツールなどは思い切ってアンインストールしましょう。代わりに本当に必要なアプリだけ残せば、スクリーンタイム自体が自然と減ります。
- 通知をオフまたは最小限に:常時光る通知は注意力を奪います。メールやSNSなど、大半のアプリのプッシュ通知は切ってしまいましょう。重要な連絡手段(電話や仕事チャットなど)だけ通知オンにして、他は自分が開いた時に確認すれば十分です。通知の断捨離だけでも、かなりスマホに触る回数が減るはずです。
- ホーム画面を整理:ミニマリストの中には、ホーム画面の1ページ目に置くアプリを4~5個程度に絞る人もいます。見る度に目に入るアイコンが少なければ、「とりあえず開いてしまう」衝動を抑えられます。フォルダにまとめて隠すのも有効です。
このようなデジタル環境の整理整頓を行うと、自分にとって何が本当に必要かが明確になります。
「なぜこのアプリが必要なのか?」と問いながらスマホをお掃除してみてください。
一度スッキリさせれば、あとは増やしすぎないよう定期的に見直すだけです。情報との付き合い方が劇的にシンプルになり、心も軽やかになるでしょう。
ランニングログの“データ依存”を防ぐコツ
最後に、ランニング愛好者ならではのデジタル依存に注意しましょう。それはランニングログのデータ依存です。
最近はGPSウォッチやスマホアプリで走行距離やペース、心拍数など細かく記録できますが、これにハマりすぎると数字に縛られるストレスを生む恐れがあります。
せっかくスマホから離れるために走っているのに、結局データを逐一チェックしていては本末転倒ですよね。
データ依存を防ぐコツは「記録はするが、リアルタイムでは見過ぎない」ことです。
例えばGPSウォッチを使う場合、走行中は画面を見ないよう心がけます(もしくは画面オフ設定にする)。記録は自動で取っておき、分析は走り終わって落ち着いてから行いましょう。
走っている最中はペースや距離にとらわれず自分の感覚に集中するランを取り入れてみてください。タイムを気にしない「ファンラン」の日を作るのも良いでしょう。
また、データをSNSに毎回投稿している人は、時にはシェアしないランを楽しむのも一案です。「誰かに見せるため」ではなく自分のためだけに走ることで、純粋なランニングの喜びが感じられます。
要は、デジタルツールはあくまで補助と割り切ることです。身体と心の声に耳を傾けることこそ、本来のランニングの醍醐味。数字はその次です。データに振り回されず上手に活用することで、ランニングもデジタルデトックスも両立して楽しめるでしょう。
FAQ:よくある質問と回答
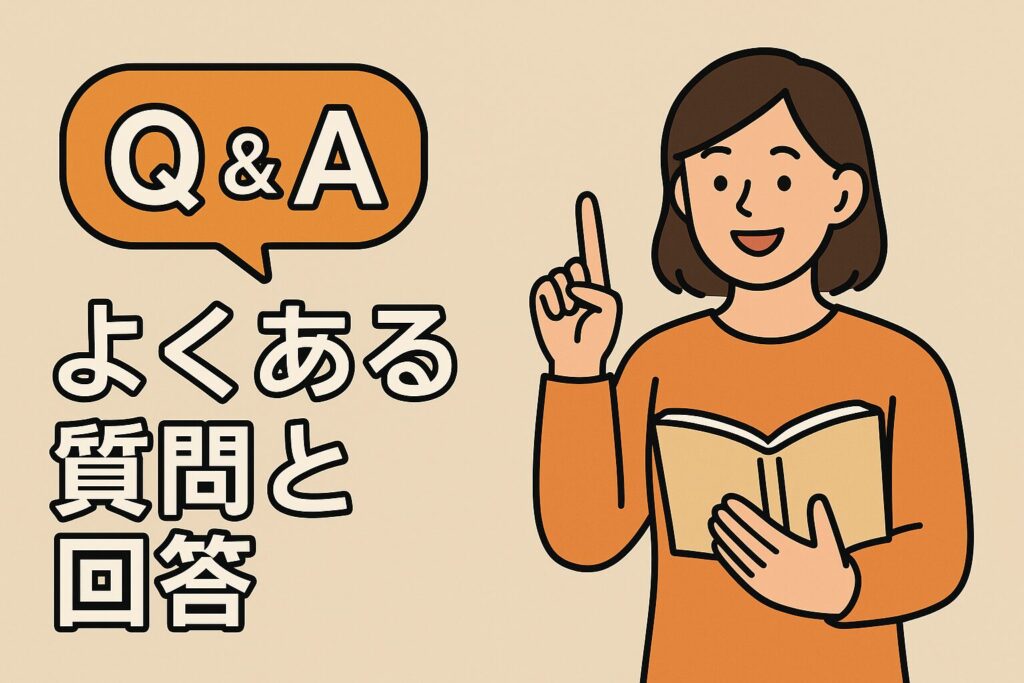
最後に、デジタルデトックス×ランニングを始めるにあたって、いだきそうな疑問や不安にQ&A形式でまとめました。
Q:音楽なしで走れる?
Q. いつも音楽やラジオを聴きながら走っているのですが、デジタルデトックスのためには音楽も無しで走るべきでしょうか?無音で走るなんて退屈しそうで不安です…。
A. 最初は音楽なしに抵抗があるかもしれませんが、無音ランも慣れるとそれはそれで楽しくなります。音楽がないと確かに最初は物足りないですが、その代わりに自然の音や自分の足音が聞こえてきます。鳥のさえずりや風を切る音に耳を傾けたり、空気の温度を感じたり、むしろ新鮮な発見があるはずです。
走るランニングフォームに集中して効率のいいランニングフォームを追求してみてもいいかもしれません。
ケガ予防のためにも正しいランニングフォームは身に着けたいところ。詳しくはこちらで解説しています。
どうしても退屈な場合は、自然音や環境音を再生するのも手です。波の音や森のざわめきといったBGMなら刺激が少なく、リラック効果があります。または音楽を完全に止めるのではなく、週に一度は無音ランの日を作るなど段階的に挑戦してみてください。
無音で走れるようになると、雑念が減ってペース配分に集中できるなどランニングそのものの質も向上します。安全面でも外の音に集中できた方が事故防止になります。
いろんな形でのランニングを楽しんでみてください。
私は普段はオーディブルで聞く読書をしながら走っていますが、週に2日くらいは無音でランニングをしています。オーディブルを使ったランニングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
そして安全に走るためにはイヤホンはオープンイヤー型がおすすめ。以下の記事のHUAWEI FreeClipがオシャレでおすすめです。

Q:緊急連絡が来たらどうする?
Q. ランニング中にスマホを家に置いていった場合、万一家族から緊急の連絡が来たらどうしようと不安です。常にスマホを持っていないと落ち着かなくて…。
A. 心配であれば完全に電源OFFにしなくてもOKです。前述のステップ3でも触れたように、スマホを持って走る場合はおやすみモード(Do Not Disturb)などで通知を遮断しつつ、特定の重要連絡先だけ通話が通る設定にしておきましょう。こうすれば緊急の電話は受けられますし、本当に必要な時だけ対応できます。
重要なのは「常に全部オン」でなくても必要最低限つながっていればよいと割り切ることです。通知をオフにするだけで走っている間はスマホと距離を置くことができます。
Q:雨・猛暑・寒波の日の代替案
Q. 決めた日に限って雨だったり、真夏の猛暑日や冬の寒波で外を走るのが難しいことがあります。そんな日は無理せずスマホで室内娯楽に走ってしまいがちですが、何か良い代替案はありますか?
A. 天候不良や極端な気温の日は、無理に屋外ランにこだわらなくてOKです。ただし「走れない=一日中デジタル漬け」にならないよう、室内でできる運動や活動を代替しましょう。
例えば雨の日は、室内でヨガやピラティス、筋トレはいかがでしょうか。ヨガマット一枚あればできるストレッチ系エクササイズが手軽でおすすめ。
運動にこだわらず、いつもは走っている時間を読書に使うという手もあると思います。
天気が悪いからといってスマホに時間を使わず、スマホ無しでできるプランBを用意しておくことが大切です。
続かなかったときのリカバリープラン
Q. 何度かチャレンジしたのですが、忙しさに負けてデジタルデトックスやランニングが続かなくなってしまいました…。途中で挫折した場合、どのように立て直すと良いでしょうか?
A. 続かなかった自分を責める必要はありません。むしろ再スタートのチャンスだと捉えましょう。もう一度目的、目標を思い出し、朝10分など小さい目標から達成しながら再スタートしてみてください。続けやすい時間帯に見直すというのも手だと思います。
人間誰しも波があります。大事なのはやめてしまわず、形を変えてでも続けることです。一度リズムが乱れても原因を確認して、以前より無理なく習慣化していきましょう。
データ記録用スマートウォッチはOK?
Q. ランニングログのためにGPSスマートウォッチを使っています。デジタルデトックス的には、腕につけるデバイスもやめた方が良いのでしょうか?通知はオフにしていますが気になっています。
A. どこまでデジタルデトックスを求めるか、個人の判断にもよりますが通知さえオフになっていれば、ランニング用のスマートウォッチやフィットネストラッカーを使うのは問題ないと思います。GPS機能付きの場合、むしろスマホを持たずに済む分デジタルデトックスには効果的と言えます。
ランニングの観点でいえば心拍数やペースの管理という意味でスマートウォッチは必須だと思うので、スマートウォッチの活用はOKと考えてます。



まとめ:30分オフラインが人生に生む3つの余白


スマホに支配されていた日常にランニングというオフライン習慣を取り入れることで、人生には「時間の余白」「心の余白」が生まれます。
できた余白で自然を感じたり、読書を楽しんだり、家族との会話を楽しんだり、オフラインの良さを感じて人生の質を高めていきましょう。
デジタルデトックス×ランニングは、忙しい現代人に残された貴重な余白創出の手段です。まずは今日から一歩踏み出してみませんか?きっと昨日とは違う新しい生活がスタートするはずです。
本ブログは「40代から楽に楽しくはじめるランニング」をコンセプトに、主に日々のランニング練習に使えるシューズのレビュー記事を公開しています。
「他のシューズとの比較が知りたい」という方は、こちらの記事から気になるシューズの比較記事を探してみてください!